皆さん、こんにちは。当ブログを運営しているニックです。
いつも「ヘルスケアや美容」、「ひよこものがたり」など、さまざまなテーマで記事をお届けしていますが、今回は少し趣向を変えて、「視覚障害」というテーマに焦点を当ててみたいと思います。
実は私自身、視覚障害を抱えて生活しています。SNSを通じて多くの視覚障害に関する情報に触れる中で、誤解や偏見に心を痛めることも少なくありません。
だからこそ、当事者としての視点から、視覚障害に対する理解を深めるきっかけとなるような記事を書きたいと思いました。
このシリーズでは、全7回にわたって視覚障害にまつわる誤解や、その背景にある事実や、視覚障害者がどのように社会と関わっているのかをお伝えしていきます。
誤解や偏見を解消していくことは、誰もが安心して暮らせる共生社会への第一歩だと思います。
ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しく思います。
はじめに
視覚障害と聞くと、多くの人たちは「全く目が見えない」というイメージを抱きがちです。
しかし、この誤った認識こそが、視覚障害者に対する様々な誤解の根源となっているように思います。
実際には、身体障害者手帳を所持する視覚障害者のうち、約7割程度が「ロービジョン(弱視)」であり、残された視力を活用しながら日常生活を送っています。
ロービジョンの人たちの見え方についても様々であり、見え方に応じて拡大表示機能や音声読み上げ機能などを利用してスマートフォンを操作する人や、白杖を地面から話して補助的に使用するなど、多様な方法で生活しています。
また、「全盲者は何もできない。」という偏見も根深いですが、就労や社会活動に参加して自立した生活を送っている人は少なくありません。
このような視覚障害の多様性への理解不足が、不必要な偏見や、時には善意からくる過剰な配慮を生み出し、視覚障害者の自立を阻害する要因となっています 。
これらの誤解は、単なる知識不足に留まらず、視覚障害者の日常生活における具体的な不便さや、社会参加における障壁、さらには差別へとつながる深刻な影響を及ぼします。
例えば、就職面接での能力の不当な評価、公共の場での不必要な干渉や、あるいは適切な支援の欠如などが挙げられます。
これらの状況は、視覚障害者の自立と社会参加を阻害するだけでなく、結果として社会全体に経済的・社会的に大きなコストをもたらしていることが指摘されています 。
特に「視覚障害者=全盲」という固定観念は、個人の経験と社会全体の構造に深く影響を及ぼしています。
この根本的な誤解は、ロービジョンの人々がスマートフォンを使用したり、白杖を持っていたりする際に、周囲から「本当に見えていないのか?」といった疑念や誤った批判の目を向けられる状況を生み出しています。
このような状況は、単に不快感を抱くだけでなく、視覚障害を持つ個人に著しい精神的苦痛を与え、時には公共の場での活動(例えば、電車内でのスマートフォン使用)を避けるようになるなど、自己制限的な行動につながることがあります。
これは、視覚障害の多様性(弱視から全盲まで)に関する社会教育の欠如を示しており、この社会的な無知が、個人の偏見、過剰な配慮、そして雇用や社会参加における障壁として現れ、最終的には膨大な経済的およびQOL(生活の質)の低下につながっています。
本テーマ(全7回)では、視覚障害者に対する一般的な誤解を一つ一つ丁寧に解き明かし、その背景にある真実を伝えることを目指していきます。
これにより、読者の皆さんが視覚障害者とのより良い関係を築き、真にインクルーシブで共生できる社会の実現に貢献するための具体的な一歩を踏み出すきっかけとなることを願っています。
視覚障害の誤解あれこれ
スマートフォンの誤解
誤解①:電車で席を譲ったらスマホを見始めて唖然とした。
説明:スマートフォンには拡大表示、音声読み上げ、画面読み上げなどのアクセシビリティ機能があり、ロービジョン者も全盲者もそれらを活用して情報を得たり、連絡を取り合ったりしています。
誤解②:コンビニで商品にスマートフォンのカメラを向けていた。
説明:単にパッケージの文字を拡大している場合や、AIで画像認識して商品の説明を音声で確認している可能性があります。ロービジョンや全盲の方にとって、商品のパッケージや文字は見えづらい、あるいはまったく見えないことがあります。そのため、スマートフォンは「目の代わり」として使われる重要なツールなのです。
白杖の誤解
誤解①:「白杖を持っているのに障害物を目で見て回避した」
説明:ロービジョンの方は、限られた視力で障害物を確認できる場合もありますが、白杖は周囲に「視覚障害がある」ことを知らせる役割も果たしています。見えているように見える行動があっても、それは残存視力を活用しているだけであり、誤解すべきではありません。
誤解②:「普段白杖を持っているのに白杖を持たずに歩いていた」
説明:視覚障害の程度や状況によって、白杖の使用は柔軟に変わります。明るい場所や慣れた環境では白杖を使わないこともありますし、逆に暗い場所や混雑した場所では使用することもあります。白杖の使用=常に必要という固定観念は誤りです。
全盲の誤解
誤解①:介助が無いと日常生活がままならない。
説明:全盲の方でも、点字、音声機器、生活訓練などを通じて自立した生活を送っている人は多くいます。調理、移動、仕事なども工夫と支援機器を活用することで可能です。もちろん場面によっては介助が必要なこともありますが、「常に誰かの助けが必要」というのは偏見であり、本人の能力や努力を過小評価することにつながります。
誤解②:全盲の人はまったく見えない
説明:「全盲」と言っても、視覚の状態は人によって異なります。完全に光を感じない人もいれば、明暗の区別ができる人、ぼんやりとした形や色がわかる人もいます。つまり、「全盲=完全な暗闇」というイメージは一面的であり、実際にはさまざまな見え方があります。
まとめ
視覚障害という言葉を聞いたとき、多くの人は「全く目が見えない状態」を思い浮かべるかもしれません。しかし、現実には「ロービジョン」と呼ばれる弱視の状態を含め、多様な見え方が存在しています。
この多様性を正しく理解しないまま「スマホを使っているのに障害があるの?」「白杖を持っているのに見えているように見える」などの誤解や偏見が生まれ、時に視覚障害者本人を傷つけ、社会参加を困難にしています。
私自身も視覚障害の当事者として、こうした誤解に何度も直面してきました。そのたびに「見え方にはいろいろあるんだ」という基本的な知識がもっと広まってほしいと感じています。
本シリーズでは、視覚障害に関する典型的な誤解を一つひとつ取り上げ、背景にある事実をわかりやすくお伝えしていきます。
視覚障害=全盲だけではない。
視覚障害があってもスマホを使える。
見え方も、生き方も、人それぞれ。
この記事が、視覚障害について少しでも理解を深めるきっかけとなり、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に近づく一歩になれば、これ以上嬉しいことはありません。
次回以降も、ぜひお付き合いください。


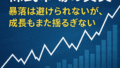
コメント