はじめに:視覚障害者とのコミュニケーション
視覚障害者が安心して社会に参加し、自立した生活を送るためには、周囲の皆さんの理解と少しの配慮がとても大切になってきます。
円滑なコミュニケーションと適切な支援は、視覚障害者の可能性を広げ、誰もが共に暮らせる社会づくりにつながります。
いくつかの基本的なポイントを知っていただくことで、双方が安心してコミュニケーションをとることができます。
声かけの基本:驚かせず、具体的に
視覚障害者に声をかける際は、まず自分の存在を知らせ、驚かせないように正面から、「私は○○ですが、何かお手伝いしましょうか?」と具体的に提案していただくことが推奨されています。
移動中は歩くことに集中しているため、立ち止まっている時が声かけの良いタイミングです。ただし、車道やホームに向かっている、人と衝突しそうな緊急時は、ためらわずに注意を促してくださると助かります。
緊急時以外は、無言で腕を掴んだり、白杖を掴んだりする行為は、相手に驚きや不安感を与えることがあるため、避けていただけたらと思います。
声をかけても話しかけられていることに気づいていない様子であれば、話しかけながら肩を軽く叩いて知らせていただくのも有効です。
指示語を避け、具体的な言葉で伝える
「こちら」「あちら」「そこ」といった指示語は、視覚障害者には情報として伝わりにくいです。
そのため、「30センチ右」「2歩前」「そのまま真っすぐ歩くと20m程度先の左手にコンビニがあります」のように、位置関係や方向を具体的に伝えていただけると助かります。
対面で方向を指示する際には、視覚障害者から見た方向で説明していただけると、より伝わりやすくなります。
言葉で説明しづらいものや、手で触れた方が理解しやすいものについては、手をとって触らせながら説明していただくのも助かります。
例えば、新しい家電製品の操作ボタンを説明する際に、実際に指で触れさせながら説明すると、理解がしやすいです。
状況説明と相づちの重要性
会話中は、首を振るだけでなく、声に出して相づちを打つことで、話が通じていることがわかります。
これにより、スムーズなコミュニケーションが図れます。
相手を待たせる際や、一時的に席を外す際は、「○○をしているので少し待ってください」「少し席を外します」など、状況を具体的に伝えていただけると助かります。
何も言わずに立ち去ると、相手は不安を感じたり、まだあなたがそこにいると思って話し続けたりする可能性があるからです。
介助歩行・誘導の正しい方法
視覚障碍者が介助が必要な様子であれば、まず「どうかしましたか?」「お手伝いしましょうか?」と声をかけてください。
誘導が必要な場合は、視覚障害者の半歩前に立ち、肘か肩を掴ませてください。
誘導者は自然な姿勢で歩き出し、視覚障害者は自然に後ろからついてくる形となります。
障害物にぶつからないよう、2人分の幅を確保して歩くようにお願いします。
狭い場所を通る際は、その旨を相手に伝え、相手が掴んでいる腕を背中に回してもらえると、スムーズに移動できます 。
階段や改札など、相手に準備が必要な場面では、直前ではなく「もうすぐ改札です」「10m先に下り階段です」など、ある程度準備ができる間をとって伝えていただけるとありがたいです。
目的地に到着したら、場所や方向を具体的に説明し、相手が理解できているかを確認して誘導を終えます。
何もない空間では不安を感じることもあるため、点字ブロックや壁などの位置を教えていただけると現在地や方向が理解しやすくなります。
周囲の状況(例:「中は混雑しているようです」「雨雲が出てきました」「前から人が歩いてきているので少し左によけます」)や、路面の状況、景色、お店の情報などをさりげなく伝えていただくことも、視覚障害者にとって貴重な情報共有となり、大変助かります。
家庭や日常生活での具体的な配慮
家庭内においても、指示語を避け、具体的に状況を伝えてもらえると助かります。
例えば、一緒にテレビを見ているときに映像でしか伝わらない場面で説明を加えたり、「1m前にゴミ箱がある」など、日常の些細な情報共有が、視覚障害者にとって大きな助けとなります。
特に危険な要素がない限り、本人が自分でできることを増やそうとしたり、何か工夫できることを考えている場面では、見守っていただくことも重要です 。
自宅内でも、特に通路上に角ばったものや不安定なものを置かないよう注意が必要です。
扉は半開きになっていると危険なため、きちんと閉めるか、開ける場合は最後まで開けて固定することが望ましいです。
配線コードや滑りやすい物を通り道に置かないなど、安全な環境づくりも重要です。
自分の位置や方向を見失ったり、目的の物が見つけられない場合に備え、触って分かる目印(例:使用頻度の高いドアノブにカバー、電気製品のボタンに盛り上がりのあるシール)をつけると、操作しやすくなります。
使用頻度の高い物は置く位置を決めておくと、探す手間が省け、生活が楽になります(例:ティッシュ、リモコン、ゴミ箱、浴室の石鹸、冷蔵庫の飲み物、タンスの衣類など)。
これらの物がいつもと違う場所にあるとどこにあるか見つけるのに苦労してしまいます。使ったものは元の場所に置くか、物品を動かした場合はその旨を伝えていただけたら助かります。
廊下や部屋の中の通り道になる場所へ物を置くことは避け、一時的に置く場合は、必ず一声かけて注意を促していただけたらと思います。
食事の際も、食卓に並んでいるお皿やその中身を説明し、食べられないものや注意が必要なもの(レモン、わさびなど)がある場合は伝えてもらえると助かります。
黙って配置を変えると戸惑ったりひっくり返すなどの事故につながるため、状況が変わった場合は「○○のお皿さげるね」「○○のお皿を前に置くから湯飲みを右にずらしたよ」などと具体的に伝えてください。
小皿に取り分けた場合も、何をお皿に置いたかを説明し、残っている場合は「まだ○○が残っているよ」と教えてもらえると嬉しいです。
視力が活用できる場合は、色のコントラストに配慮した食器(例:黒っぽい茶碗にご飯、白っぽい器に味噌汁)を使うと視認性が上がり、食べやすくなります。
おわりに:より良いコミュニケーションと支援のために
私たちは「支援」というと、「何かをしてあげること」と考えがちです。しかし、本当に大切なのは、一人ひとりの個性や状況に合わせた「対話」だと思います。
大切なのは、「できないこと」ではなく、「どうすればできるか」を一緒に考えてもらうことです。
私たちが主体となって「こんなサポートがあれば、もっと自由に動ける」「こうすれば、もっと活動が広がる」といった希望を伝え、それに耳を傾けてもらうことで、支援は一方的なものではなく、協力的な関係へと変わります。
画一的なマニュアル通りの支援や、よかれと思っての過剰なサポートは、かえって私たちの意図とずれてしまうことがあります。だからこそ、その人自身の声に耳を傾けてほしいのです。それは、私たちが自分らしく生き、社会の一員として尊重されるために、とても重要なことです。
支援とは、お互いを理解し、協力し合う関係を築くことだと思います。そうした関わりが、私たちと社会をつなぐ、より良いコミュニケーションにつながっていくと信じています。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
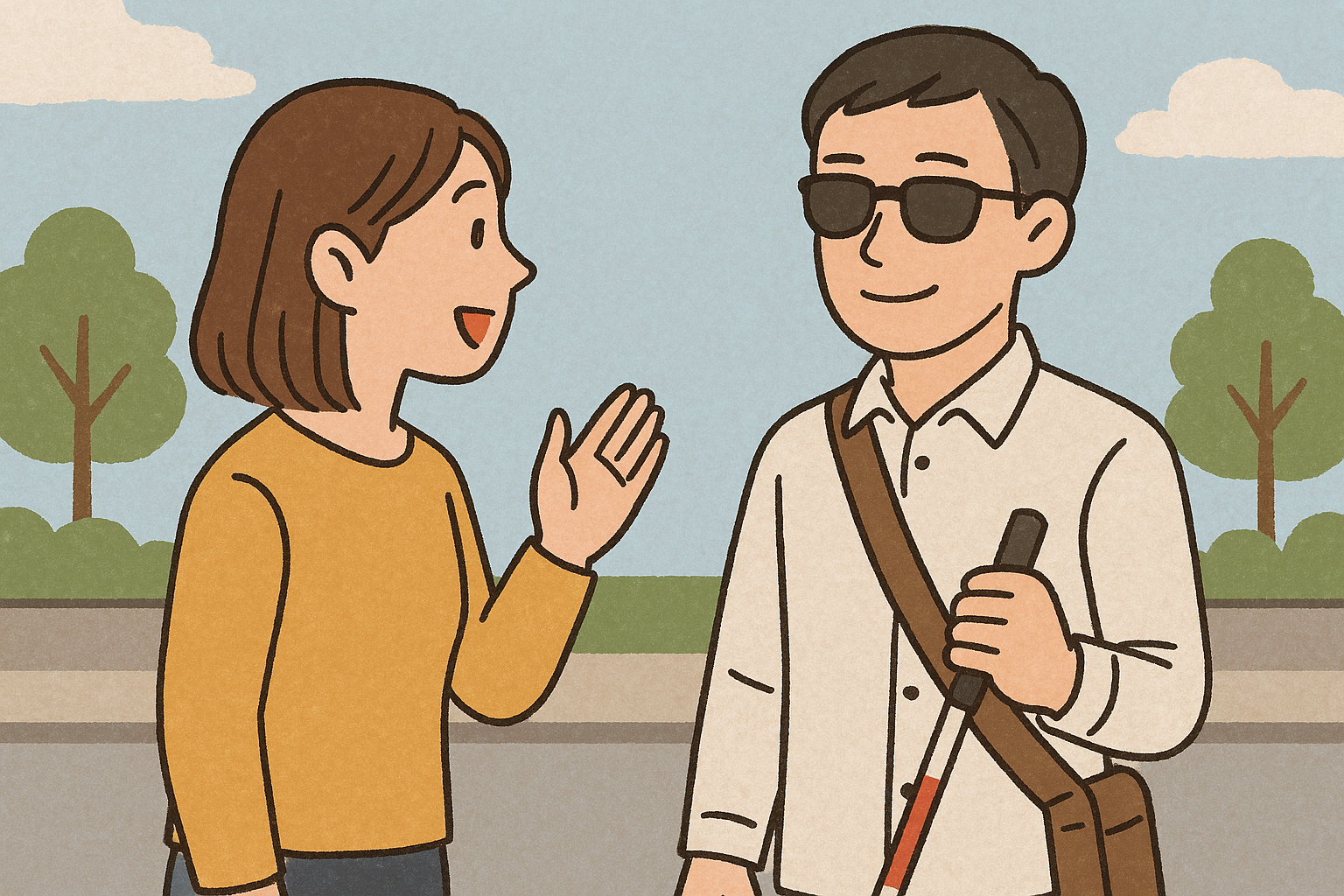


コメント