視覚障害者への誤解や偏見を減らすべく、全7回にわたって様々な啓発記事を執筆してきました。
本記事では最終回として、ロービジョン(弱視)の方々がどのような「見え方」をしているのかについて、皆さんに知っていただきたいと思います。
「見え方」を理解することは、視覚障害に対する誤解や偏見を減らす大きな一歩です。
一口に「見えにくい」と言っても、その程度や特徴は人によって大きく異なります。
こうした「見え方」の違いを知ることで、視覚障害者への誤解を減らし、適切なかかわり方ができるようになります。
そして何より、「見えにくさ」はその人の能力や可能性を決して否定するものではないということを、改めて心に留めていただければと思います。
ロービジョンの様々な「見え方」
以下は、ロービジョン(弱視)の人たちの「見え方」をまとめたものです。
これらの見え方は、実際には症状の強弱があったり複数が重なって現れたりすることもあります。
1. 中心暗点(中心が見えない)
視野の中心が見えない・見えにくい状態。加齢黄斑変性などで見られる。顔の認識や文字の読み取りが困難。
2. 周辺視野欠損(周囲が見えない)
視野の中心は見えるが、周囲が欠けている。欠けている部分は黒く見えるわけではなく、そこを認識できない。緑内障などで見られる。歩行時に障害物に気づきにくい。
3. 視野狭窄(トンネル視野)
視野が極端に狭く、まるで筒の中から見ているような状態。網膜色素変性症などで見られる。周囲の状況把握が困難。
4. 霧視(かすみがかかったように見える)
全体的に白っぽく、すりガラスやくもった眼鏡越しに見ているように見える。角膜混濁・白内障などで見られる。光のまぶしさを強く感じることもある。
5. 光視症・光過敏(光がまぶしく感じる)
通常の光でも非常にまぶしく感じる。逆光や日差しの強い場所では視界がほぼ失われることも。網膜疾患などで見られる。
6. 夜盲
明るい所では見えるが、暗い所で見えない・見えにくくなる。昼間は普通に生活できている人も夜間になると見えなくなり、周囲から理解されないことも。網膜色素変性症などにみられる。
7. 像の歪み(物が曲がって見える)
直線が波打って見えたり、物の形が歪んで見える。黄斑部の障害で見られる。文字の読み取りや顔の認識に支障が出る。
8. 視力低下(ぼやけて見える)
全体的にピントが合わず、ぼやけて見える。眼鏡でも矯正できない場合がある。多くの疾患で見られる一般的な症状。
9. 色覚異常(色の識別が困難)
特定の色の区別が難しくなる。色の濃淡や明暗で判断する必要がある。先天性または後天性の色覚障害で見られる。
10.眼瞼痙攣
まぶたを閉じる眼輪筋の痙攣で目が開かなくなる。重症例だとほとんど目が閉じたままで、機能的な失明をきたす。
最後に
視覚障害者の「見え方」は十人十色であり、その違いを知ることは、共生社会への第一歩です。私たち一人ひとりが、見えにくさを「その人らしさ」の一部として受け止め、理解しようとする姿勢こそが、偏見や誤解をなくす力になります。
7回にわたる連載を通じて、視覚障害に対する正しい知識と、共に生きるためのヒントをお届けしてきました。これらの情報が、皆さんの中にある「気づき」や「やさしさ」の種となり、誰もが安心して暮らせる社会づくりにつながることを願っています。
見え方が違っても、できることはたくさんあります。違いを知り、違いを認め合うことから、真の共生が始まります。
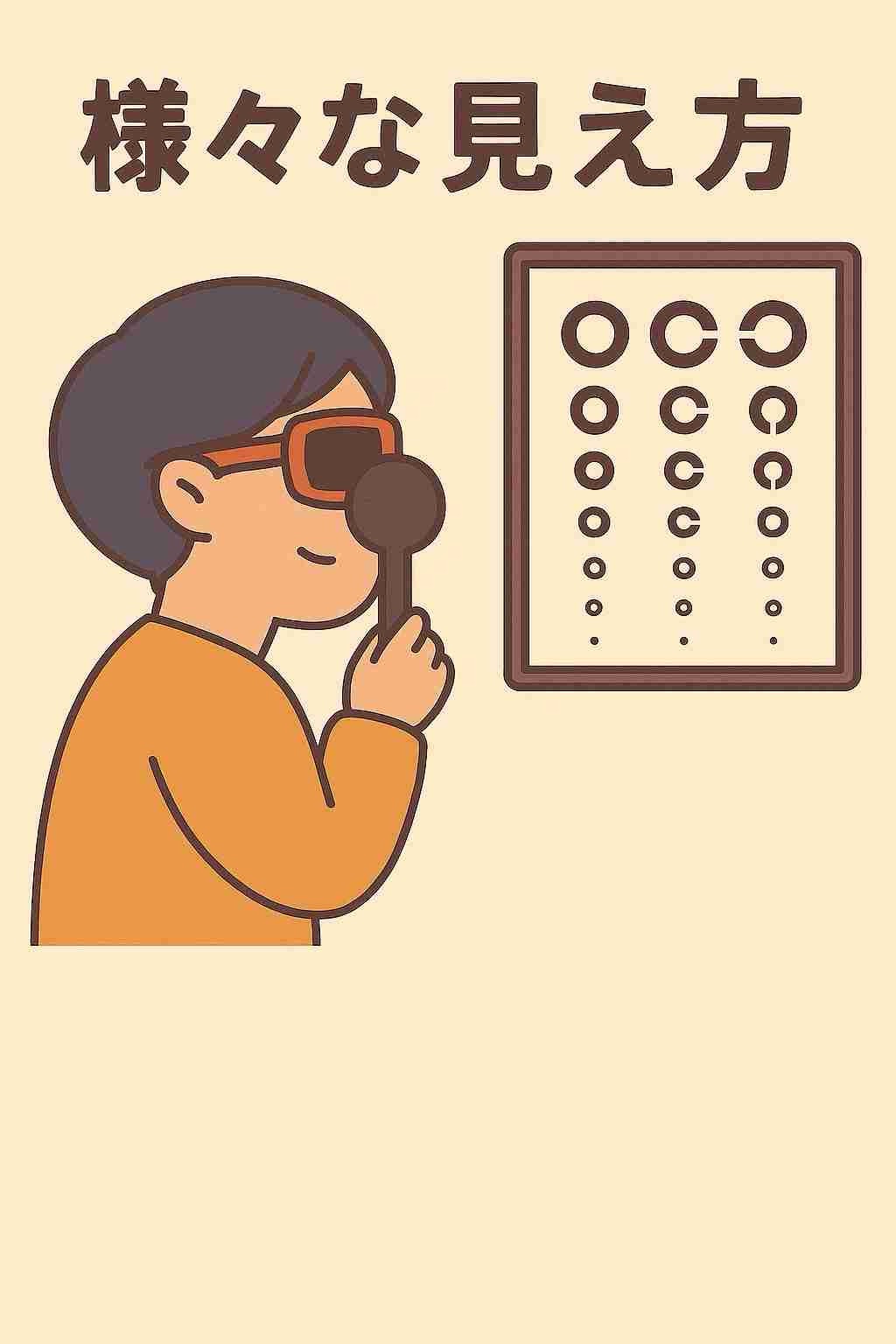
No responses yet